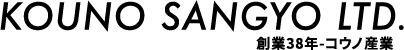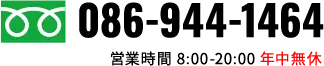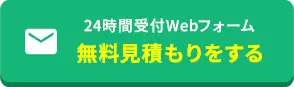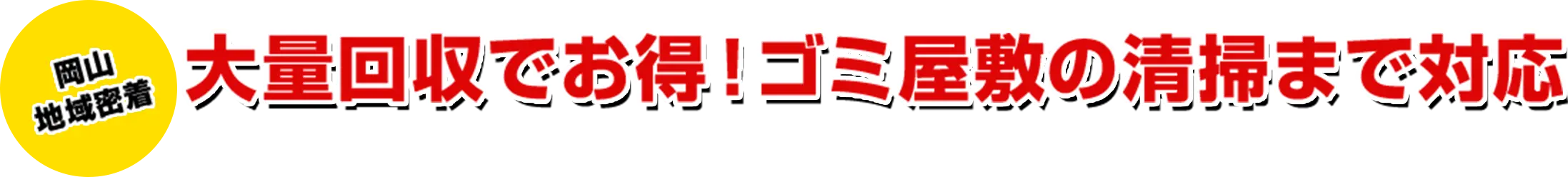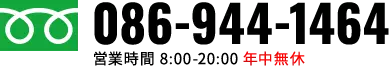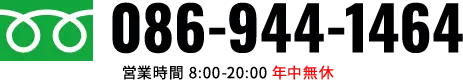COLUMN お役立ちコラム
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理のやり方などを徹底解説

「一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理はどうやってやるの?」や「責任は誰にあるの?」といったことが気になる方は多いのではないでしょうか。
昨今、単身で生活している高齢者が多いことや、身寄りがない単身者などの孤独死が問題になっていますが、このようなケースでも遺品整理は必要になるため、前もって知識を身につけておくことが求められます。
この記事では「一人暮らしの遺品整理」に関して、遺品整理のプロがやり方や注意点などをわかりやすく解説します。
目次
一人暮らしで亡くなった場合の対処
一人暮らしで亡くなった場合、ほとんどのケースは以下のような流れを辿ります。
- 警察による検死
- 死亡届の提出および火葬許可証の取得
- 葬儀および火葬
- 遺品整理
一人暮らしで亡くなった場合、法定相続人と呼ばれる人物に事後処理の責任が生じます。多くの場合、亡くなった方の子供や配偶者、さらには親戚などの家族が対象です。
最も優先されることは「警察による検死」と「死亡届の提出および火葬許可証の取得」で、事件性の有無を警察に証明してもらったうえで、死亡が発覚した時点から7日以内に死亡届を提出し、不届による罰則を避けなければいけません。
その後、葬儀と火葬を済ませてから遺品整理に着手する流れです。一般的に、遺品整理は四十九日法要を終えてから着手することが多いとされていますが、故人や家族の状況によってはその限りではありません。
遺品整理はいつ始めるべきか?遺品整理を始める適切なタイミングについては、以下の記事を参考にしてください!
遺品整理は49日前に済ませるべき?遺品整理のプロがそのメリットと注意点を解説
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理のやり方
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理のやり方は以下を参考にして下さい。
- 各種手続き
- 遺産や遺品の全容を把握する
- 遺品整理の計画を立てる
- 遺品整理業者の選定
- 片付け
上記について解説します。
各種手続き
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理は「各種手続き」から始まります。具体的には、警察への連絡、死亡診断書または死体検案書の取得、死亡届の提出、そして葬儀社の手配などです。
とりわけ、警察への連絡と死亡届の提出は、罰則や時間の制限があるため、速やかに対処しなければなりません。
遺産や遺品の全容を把握する
次に着手すべきことが「遺産や遺品の全容を把握する」です。故人が残した遺産、負債、さらにはすべての遺品を把握する必要があります。
この工程をしっかり行うことで、後の片付け作業が効率的に進みやすくなるでしょう。遺品は物だけとは限らないため、預金や証券、そして負債もしっかり確認してください。
遺品整理の計画を立てる
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理では「遺品整理の計画を立てる」ことも大切です。具体的には、いつ、誰が、どうやって、いつまでに片付けるかを明確にします。
特に、遺品整理に着手する時期と終える時期を決めることがポイントです。遺品整理は、やみくもに取り組んでも片付かないため、しっかり計画を立てるようにしましょう。
遺品整理業者の選定
次に「遺品整理業者の選定」です。遺品整理の際に、必ずしも遺品整理業者を利用する必要はありませんが、物量が多い場合や人手が足りないとき、さらには遠方に住んでいるケースでは業者を利用するのが無難でしょう。
遺品整理業者は数多く存在している一方、ぼったくりや違法行為を行う悪徳業者も含まれるため、信頼できる業者を慎重に選ぶ必要があります。
片付け
最後の工程が「片付け」です。具体的には、故人が残したゴミの処理や、遺品の仕分け、処分、譲渡、そして売買などが含まれます。
片付けは、故人の家族や親戚、さらには遺品整理業者によって行われることがほとんどで、家族では対応できない事情がある場合は、遺品整理業者に任せるのが適切です。
一人暮らしの遺品整理にかかる費用相場

一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理にかかる費用相場は以下を参考にしてください。
- 1R、1K:120,000円
- 1DK、2K:200,000円~
- 1LDK、2DK、3K:300,000円~
- 2LDK、3DK:350,000円~
- 3LDK、4DK:450,000円~
- 4LDK、5DK:550,000円~
- マンションや一軒家(5LDK以上):680,000円~
一人暮らしで亡くなった際にかかる遺品整理の費用相場は、片付けの対象となる部屋の間取りや物量、そして作業量によって変動することを覚えておきましょう。
また、同じ片付け作業であっても、業者ごとに料金が異なることにも注意してください。費用を抑えたい場合は、複数の遺品整理業者に見積もってもらうことがポイントです。
岡山県で遺品整理のことなら、地域密着のコウノ産業にお任せください。業界平均を下回る価格で対応いたしますので、安心してご依頼いただけます。
一人暮らしの遺品整理でよくあるトラブル
一人暮らしの遺品整理では、以下のようなトラブルが起こりやすいといわれています。これらをあらかじめ理解しておくことで、トラブルを回避できるだけでなく、スムーズな遺品整理が可能です。
- 遺産の掌握が困難
- 遺品の仕分けが大変
- 物量が多い
- 時間的な制限
- 部屋の損傷
それぞれ解説します。
遺産の掌握が困難
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理では「遺産の掌握が困難」というトラブルが起こります。具体的には、故人の財産や負債がどれほどあるのか、すべてを把握できないことでトラブルが起こりやすくなるでしょう。
特に、相続人が遺産を引き継いだ後に、想定外の負債が発覚することもあります。また、家族間での遺産分割に影響する可能性も否定できないため、遺産の掌握は慎重に行いましょう。
遺品の仕分けが大変
「遺品の仕分けが大変」なこともよくあるトラブルです。例えば、故人の遺品を処分するもの、寄付するもの、売却するもの、さらには保管するものといったように、一つひとつ仕分けなければなりません。
物量が多い場合や、価値の判断が難しいもの、さらには誰にも相談できないケースでは、片付かない要因になってしまいます。
物量が多い
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理では「物量が多い」トラブルも挙げられます。具体的には、故人が物を溜め込む習慣があった場合や、趣味のものが多い、さらには倉庫を借りているケースなどがあります。
遺品整理では、物量が多いと片付け作業が大変になるだけでなく、時間もコストもかかるため、費用負担などが問題になりやすいでしょう。
時間的な制限
「時間的な制限」もトラブルになりやすい要素です。例えば、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、契約期間や契約内容によっては、速やかに退去することが求められるかもしれません。
故人を失った悲しみが癒えるよりも先に、遺品整理や清掃、さらには原状回復を済ませなければならないケースもあるため、精神的な負担が大きくなる可能性があります。
部屋の損傷
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理では「部屋の損傷」がトラブルになるかもしれません。具体的には、亡くなった方の発見が遅れた場合などは、腐敗が進行していることが多く、特殊清掃と呼ばれる専門的な清掃作業が必要になります。
特殊清掃にかかる費用や、清掃業者の選定などで負担が増えるでしょう。また、賃貸住宅においては、貸主が要求する原状回復を巡ってトラブルになる可能性も否定できません。
遺品整理業者選びのポイント
遺品整理業者を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてください。
- 複数の遺品整理業者に見積もってもらう
- 遺品整理に関連するサービス内容が充実しているか確認する
- 地元の業者を選ぶ
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理は、なるべく早く、なおかつ柔軟に対応してくれる業者を選ぶようにしましょう。
迅速に対応してくれやすい地元の業者を中心にして、なるべく多くの業者から現場で見積もってもらってください。
まとめ
一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理は、まずは警察や役所などの手続きが大切です。法的な義務を果たしたうえで、時間をかけて遺品整理を計画し、実行に移ってください。
遠方に住んでいる場合や時間がない、さらには人手が確保できない場合は、地元の遺品整理業者に相談することをおすすめします。
関連記事